おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\

プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
高校時代に英語を猛勉強し、校内偏差値が40→80にUP。大学では英語教育を専攻し、4年次にオーストラリアのパースへ留学。「話す」「聞く」にフォーカスを置いて、現地の人々や世界各国の留学生と交流を深めた。その結果、ケンブリッジ英検B2、TOEIC400→835を取得。現在は、海外へ行きたいけど英語に不安がある人たちのサポートや後押しをしている。
英語論文は日本語論文と書き方や構成が違います。
つまり、スムーズに英語論文の読み書きをするためには、英語論文の構成や書式、マナーを理解しておくことが役立ちます。
今回は、英語論文の書き方についてご紹介します。
「全くの英会話初心だけど英会話教室の雰囲気を知りたい」
「子供に夏休みを有意義に過ごさせたい」
「本格的に英語の勉強を始めたい」
という方には「AEON KIDS(イーオンこども英会話)」のキッズサマースクールがおすすめです!
年齢に合わせた細かなクラス分け・教材で、子供たちの英語4技能を伸ばす「AEON KIDS(イーオンこども英会話)」。キッズサマースクールは3歳~中学生まで受講でき、計4回のレッスンで英語力を高められるので短期間で成果を実感できます。
-summer-cp.png)
受付期間:〜 2024年7月27日
※対象は、はじめてイーオンキッズのレッスンを受講される方、もしくは過去にイーオンキッズへ通学いただき2024年3月末日以前に契約が終了された方
※スクールにより開講状況が異なります。ご希望の日時・クラスでのご受講ができない場合があります。
※特典企画のため、他の特典との併用はできません。
※その他受講条件については各スクールにお問い合わせください。
オンライン英会話57社を調査して厳選した「人気のおすすめオンライン英会話」のランキングをご紹介!
オンライン英会話の選び方から目的別のおすすめランキングが用意されているので自分にぴったりのオンライン英会話がきっと見つかります。
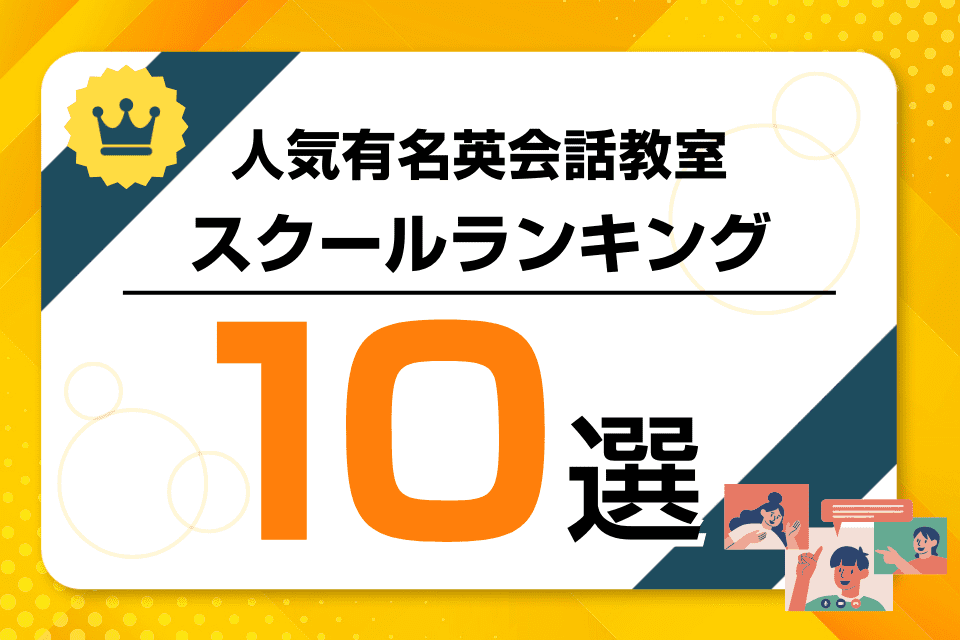
「論文」とは、学術研究の成果など、あるテーマについてまとめた文章のことです。
事実に対する客観的な意見を論理的に書いていきます。
では、英語論文を書く前に知っておくべきことを見ていきましょう。
英語論文は、その内容によって呼び方が違います。「論文」は英語で以下のように表現します。
英語論文を書く際、まず日本語で論文を作成し、それを英語に翻訳する手法をとる方もいらっしゃるでしょう。
ただしその場合は、注意が必要です。
なぜなら、日本語と英語では文章の構成が異なるからです。
つまり、そのまま文字通りに翻訳するのではなく、英語の発想で文書を組み立てなければいけません。
それを踏まえた上で、英語論文の書き方をみていきましょう。
英語論文を書くには、いくつかの手順とコツが必要です。
どんな順序で組み立てていくのが効率的なのでしょうか。
英語論文を書く前に、まずどの種類の論文なのかをはっきりさせましょう。
そして、書きたい内容と目的を明確にしてください。
内容と目的を明確にすれば、それに似た過去の論文を読み、ヒントを得ることができるでしょう。
英語論文では、一人称は不適切と言われています。
つまり、「I think 〜.」などで始まる文章はNGです。
そのため、三人称や受動態などを使うのが一般的です。
日本語では「〜だから〜である。」と、まず理由を述べてから、結論を述べる文章が一般的です。
一方、英語では「〜だ。なぜなら〜だからである。」と、まず結論を述べた後、理由を述べます。
英語論文は、長い文章よりも短くて簡潔な文章が好まれます。
1文あたり20単語前後が理想的な文章の長さと言われています。
また、短い文章は、文法ミスの回避にもつながります。
当たり前のことですが、スペルミスはNGです。
間違えないように細心の注意を払いましょう。
日本語の論文にも言えることですが、同じ単語や言い回しを何度も繰り返し使うと、文章全体が単調になります。
一方、キーワードとなる言葉は積極的に使いましょう。
論文では、フォーマルな表現が必須です。
例えば、日常的に使っている「I’m」は「I am」、「Don’t」は「Do not」が正しい文語です。
また、英語論文ならではの言葉を使う必要があります。
例えば「but」は「however」、「and」は「moreover」、「really」は「extremely」など日常会話ではあまり使わない単語を使います。
本記事では、英語論文の構成例をご紹介します。
英語論文は、以下の10で構成されています。
では、それぞれの構成部分を詳しくみていきましょう。
論文のタイトルは、とても重要です。
なぜなら、最も人の目に触れるのは「タイトル」だからです。
タイトルの目的の一つは、人を引き寄せることです。
WEBなどで検索する際、タイトルをみて、どのような内容が記載されているかを判断します。
タイトルの語数は、10〜12語程度が理想的と言われています。
読み手の興味を引くタイトルをつけましょう。
タイトルと論文の内容が一致していなければ、読み手は他の論文を探すでしょう。
つまり、タイトルは、論文内容と一致している必要があります。
タイトルを付ける際には、以下の5つのポイントを参考にしましょう。
Abstract(アブストラクト)、つまり要約は、論文の内容を簡潔にまとめた部分です。
ジャーナルにより異なりますが、一般的には200〜300語程度に要約します。
多くの人は、この要約をまず読み、論文の内容を把握します。
つまり、読み手が論文を読むかどうかを判断するもの言えるでしょう。
ですから、論文で一番伝えたい重要なことを盛り込みましょう。
Introduction(イントロダクション)では、概要の紹介と論文内容の言及をします。
まず概要の紹介として、キーワードとなる単語を交え、研究した背景をまとめます。
読み手の興味を引きつけるために、先行研究の引用をすることもできるでしょう。
続いて、論文内容の言及をします。
研究内容や目的に加え、読み手に研究の重要性を伝えてください。
また、どのような実験や解析方法を用いたか、どのような結果を得ようとしているか、なども伝えます。
序論の役割のひとつは、読み手を本論へ誘導することです。
序論の最後は、この論文から得られるメリットをまとめ、読み手の興味を引き寄せましょう。
なお、Introduction(イントロダクション)は、現在理解されていることや問われている事実を伝えるものです。
よって、現在形で伝えるのが基本です。
Material and Method(マテリアル アンド メソッド)では、研究の対象と研究の方法をまとめます。
過去形での記載が一般的です。
マテリアル アンド メソッドでは、「研究デザイン」「研究対象」「データ収集」「データ分析」などの要素に関する情報をまとめます。
例えば、実験をした場合は、装置や薬品の名前、製造会社などを記載します。
また、手法に関しては、実際に行ったことを詳細に記載することもできますが、他文献を紹介したり、引用することで容易にまとめることが可能です。
Results(リザルト)では、研究から得られた結果や発見したことをまとめます。
文章はもちろん、図や表、写真などを使って客観的にまとめることも可能です。
ここでは全ての研究結果を報告するのではなく、論文に必要な情報を中心にまとめます。
なお、実験は全て終わっているので、基本的には過去形で記載します。
Discussion(ディスカッション)では、研究結果を元に自分の解釈や議論をまとめます。
研究結果の意義、他の研究との関連や比較、発見から得られた新しい視点、新たな課題などを示すのが一般的です。
Conclusions(コンクルージョン)は、研究結果をまとめた結論です。
本文を読んだ後に結論を読むので、序論よりも具体的な内容であるべきです。
また、結果を記載しますが、要点を際立たせるために一番重要な要点だけを簡潔に記載します。
なお、得られた研究結果から、読み手に行動を促したい場合は、結論にその旨をまとめます。
Acknowledged(アクノウリッジド)では、研究に協力して下さった方や組織の名称を挙げます。
例えば、アドバイスをしてくれた方、研究機器などでお世話になった方などを挙げることができるでしょう。
また、研究を進める上で補助金や寄付金を受けた場合は、組織名を記載します。
Reference(リファレンス)では、論文を書く際に参考にした過去の論文、書籍、著者名、ページ番号などを記載します。
Appendices(アペンディクス)には、数式展開や証明、動画、写真など本文に載せることができなかった情報を捕捉資料として記載します。
ただし、複数ある場合は、原則、連番付けをし、参考文献のように本文中に言及しておく必要があります。
日本語から英語に翻訳する場合は、特に「時制」の使い分けに混乱しがちです。
時制が不自然に混じっていると、読み手は違和感を感じるでしょう。
英語は、現在形か過去形のどちらかに統一するのが基本です。
つまり、時制は混ぜません。
上記でも簡単に説明しましたが、論文での時制の流れについてご紹介します。
Abstract(要約)やIntroducition(序論)では、すでに知られている事実や一般知識、これから伝えたいことなどを伝える部分です。よって、特別な理由がない限り、現在形でまとめるのが基本です。
また、Discussion(考察)やConclusions(結論)なども現在形です。
ただし、考察や結論で研究結果を振り返る場合は、過去形を使います。
Material and Method(材料と方法)やResults(結果)は、過去に行われたことの説明です。
よって、過去形でまとめるのが基本です。
過去のリサーチ結果や研究結果をまとめる場合は、現在完了形です。
今までの研究の結果を今回の研究と比較する際にも、現在完了形でまとめましょう。
英語論文を書く際、「時制」の使い分けに注意していても、混乱しやすいものです。
ですから、最終的にはネイティブにチェックしてもらうことをおすすめします。
英語論文では、書き方のルールがあります。
特に接続詞の使い方がポイントです。
接続語がない文書は詩(ポエム)のようになってしまいます。
ここでは英語論文でよく使われている接続語を中心とした表現をご紹介します。
例文:The purpose of this study is 〜.
意味:この研究の目的は~です。
例文:The main objective of this paper is 〜.
意味:この論文の主な目的は~です。
例文:This study provides 〜.
意味:この研究は~を提供します。
例文:In this paper, the discussion centers on 〜.
意味:この論文では〜を中心に議論します。
例文:The main objective of this paper is 〜.
意味:この論文の主な目的は~です。
例文:In comparison with 〜
意味:〜と比較すると
例文:In comparison to this
意味:これと比較して
例文:However
意味:しかしながら
例文:By contrast
意味:対照的に
例文:On the other hand
意味:その一方で / 他方で
例文:Another point of view
意味:別の観点で
例文:Then again
意味:しかし / その反面
例文:Yet
意味:それにも関わらず
例文:the reason for 〜.
意味:〜の理由
例文:For this reason
意味:その理由で
例文:Accordingly
意味:結果的に
例文:As a result
意味:結果として
例文:This result suggests that 〜.
意味:この結果は~ということを提案している。
例文:Hence
意味:それゆえに
例文:Thus
意味:それゆえに
例文:Primarily
意味:第一に
例文:One example of 〜 is 〜.
意味:~のひとつの例として~があります。
例文:For example, 〜.
意味:例えば~
例文:For instance, 〜.
意味:例えば〜
例文:In particularly, 〜.
意味:特に〜
例文:Among others
意味:とりわけ
例文:Specifically
意味:具体的には
例文:Such as
意味:次のような
例文:〇〇 mentions that 〜.
意味:〇〇は~と言及しています。
例文:〇〇 states that 〜.
意味:〇〇が~と言っています。
例文:According to 〇〇, 〜.
意味:〇〇 によると~です。
例文:It has been reported that 〜.
意味:〜ということが報告されています。
例文:The figure A indicates 〜.
意味:図Aは〜を示しています。
例文:Table A shows 〜.
意味:表Aは~を示しています。
例文:What’s more
意味:さらに重要なこと
例文:Above all
意味:中でも / とりわけ
例文:Moreover
意味:その上
例文:Furthermore
意味:さらに
例文:Besides
意味:それに加えて
例文:In addition to 〜.
意味:〜に加えて
例文:Similarly
意味:同様に / 類似して
例文:Likewise
意味:同様に / なおまた
例文:Not only 〜 but also
意味:だけでなく
例文:Coupled with
意味:〜に加えて
例文:Finally
意味:最後に
例文:Lastly
意味:最後に
例文:All in all,
意味:全体的にみて
例文:It is important that 〜.
意味:~は重要
例文:Altogether
意味:結局は
例文:In conclusion
意味:結論として
例文:On the whole
意味:全体としては
例文:To sum up
意味:要約すれば
例文:Persuasive
意味:説得力のある
例文:All things considered
意味:全てを考慮して
例文:In order
意味:〜するために
例文:In other words
意味:言い換えれば / すなわち
例文:This is to say
意味:すなわち / 次の通り
例文:To put it another way
意味:言い換えると / 言い換えれば
例文:That said
意味:したがって
例文:Over a wide range
意味:広範囲にわたって
例文:to some extent
意味:ある程度
例文:under 〜 condition
意味:〜の条件で
例文:In view of 〜.
意味:〜を考慮して / 〜の点からみて
今回は、一般的な英語論文の書き方についてご紹介しました。
英語論文は基本10の分野で構成されています。
論文初心者には難しく感じるかもしれませんが、基本構成を必ず守れば、それなりの論文が完成するはずです。
でも、英語を母国語としない日本人には、文法や単語のミスがあることでしょう。
ですから、完成後は、ネイティブに必ずチェックしてもらいましょう。
無料体験回数が豊富で気軽に始められるおすすめのオンライン英会話を紹介をします。



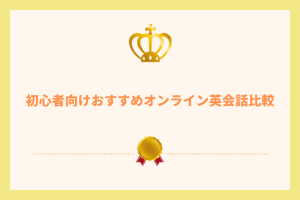
プロリア英会話のレビュー評価の評点は、オンライン英会話・通学型の英会話教室・英語コーチングを選ぶときに重要である以下のポイントと、ユーザーの口コミアンケートにより相対的に決定されています。
■ レッスン料金:レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。
・比較した全サービスの料金の中央値と比較して決定
・加点:入会金不要 / その他費用不要 / 返金制度あり / 通い放題あり
■ 講師の質と数:学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。
・比較した全サービスの講師数の中央値と比較して決定
・加点:講師(ネイティブ・日本人講師・日本語可能講師)の幅が広い / 講師の特徴が相対的に優れている
■ カリキュラム・教材・コースの充実度:カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。
・減点なし:幅広く網羅 / 教材費が完全無料
・減点:教材が少ない / 教材費が有料 or 一部有料
・加点:初心者コースあり / ビジネス対応あり / 資格試験対策(TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等)可能 / 留学サポートあり / その他優れた特徴あり / レッスン人数にバリエーションあり
■ 受講システムの使いやすさ(オンライン英会話・英語コーチングの場合):受講がしやすい環境かどうかを「学習環境・利用ツール・講師の勤務環境・予約・キャンセルシステムの使いやすさ」からレビュー評価しました。
・加点:予約・キャンセルが1時間未満でできる
・減点なし:予約・キャンセルに融通が利く / 講師の勤務環境がオフィス / アプリ or 独自システム使用可能
・減点:予約・キャンセルがフレキシブルでない / 講師の勤務環境が在宅・要確認 or 在宅・オフィス
■ 通いやすさ(英会話教室の場合):受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。
・加点:早朝レッスンあり※10時以前 / 夜間レッスンあり※20時以降 / 教室数の規模 / 最寄り駅から5分以内 / オンラインでも受講可能
※ 総合評価の評点は、上記評価軸によるレビュー評点の平均です。
※ 評点は、カリキュラムやスクールの特徴・プロリア英会話に寄せられた口コミなどをもとに、記事ごとのその特性にあわせて点数に重み付けを加点し、相対的に決定しています。
※ TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等、資格特化の記事にはスコアアップの実績有無を加味するなど、特定の記事にレビュー評価の軸を追加しています。
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
高校時代に英語を猛勉強し、校内偏差値が40→80にUP。大学では英語教育を専攻し、4年次にオーストラリアのパースへ留学。「話す」「聞く」にフォーカスを置いて、現地の人々や世界各国の留学生と交流を深めた。その結果、ケンブリッジ英検B2、TOEIC400→835を取得。現在は、海外へ行きたいけど英語に不安がある人たちのサポートや後押しをしている。









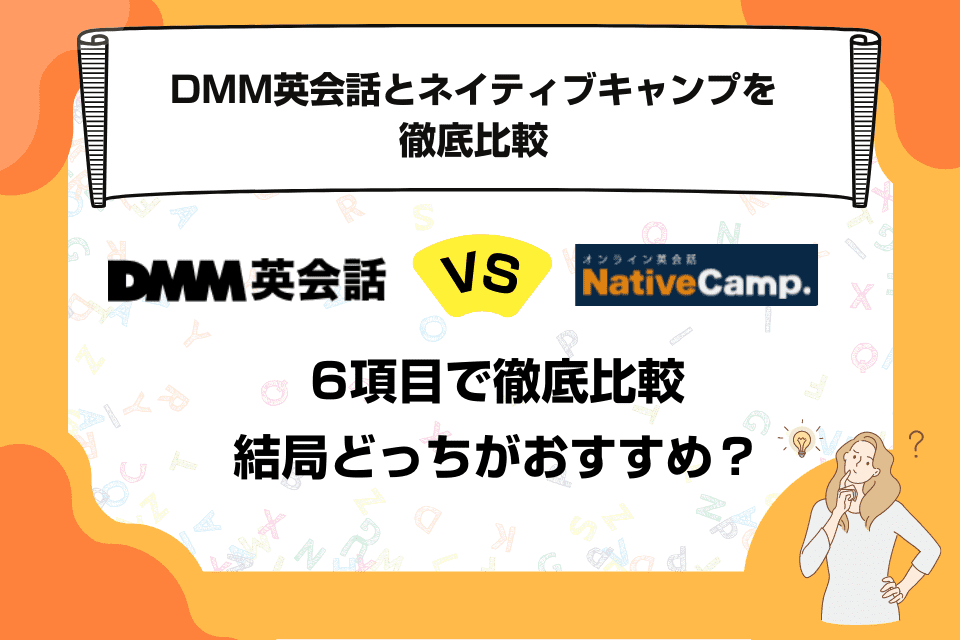


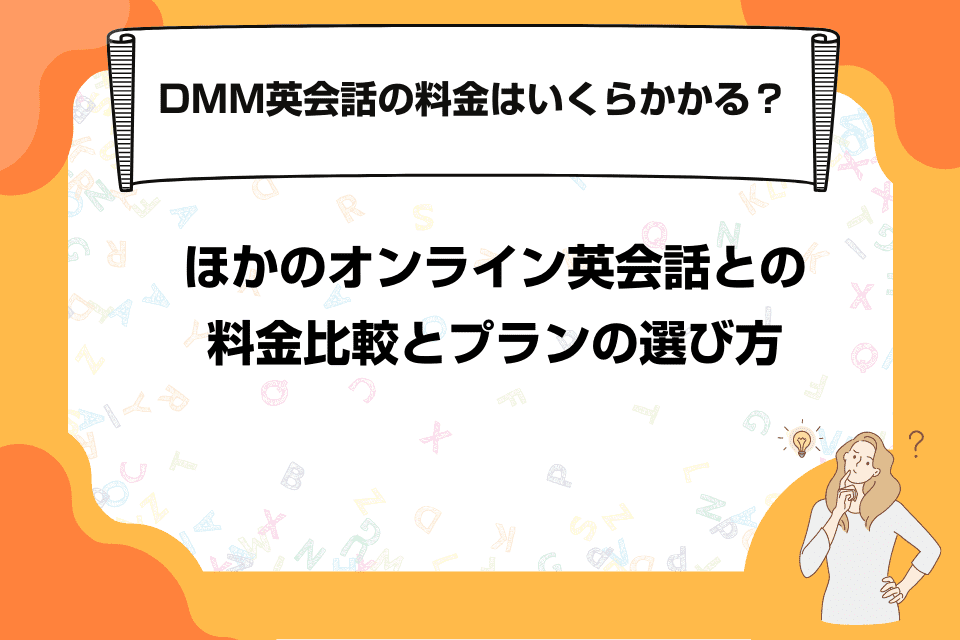
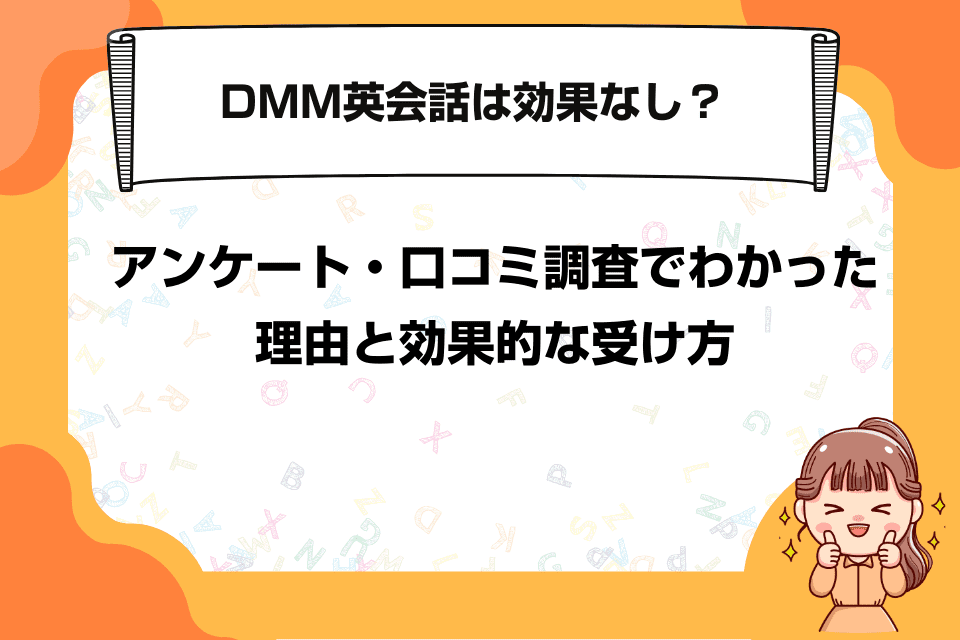
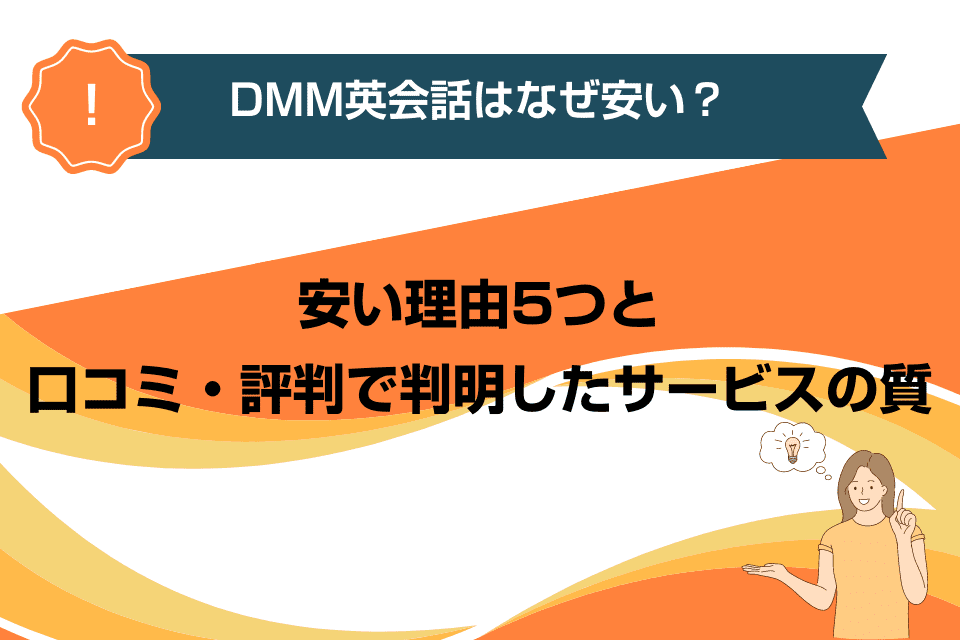
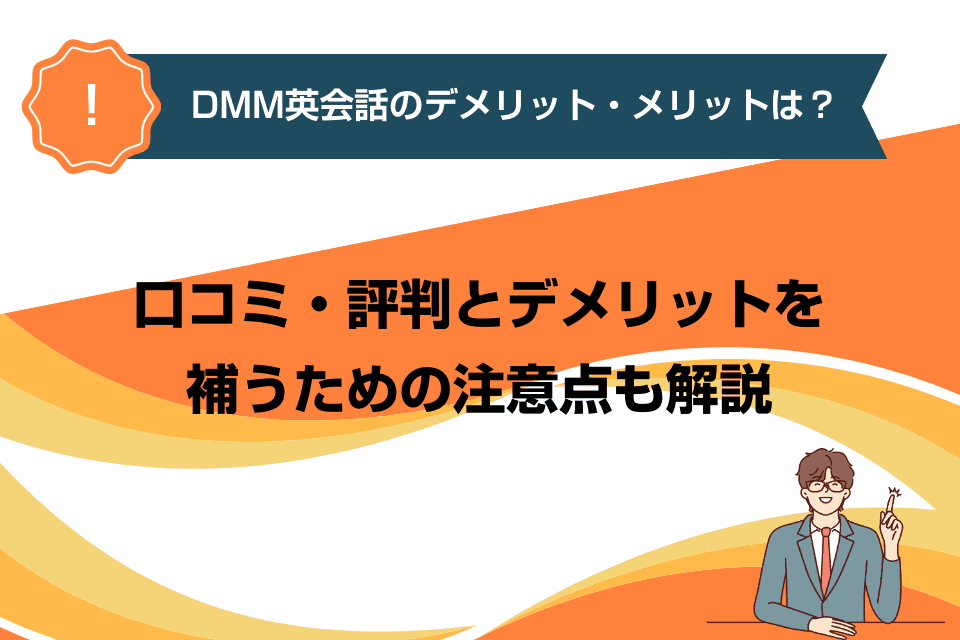
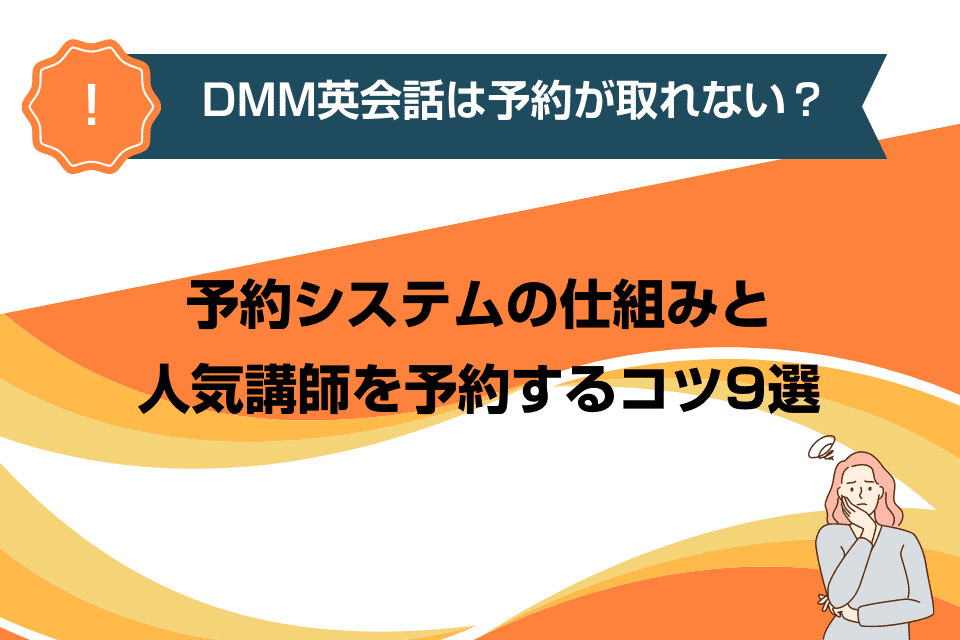
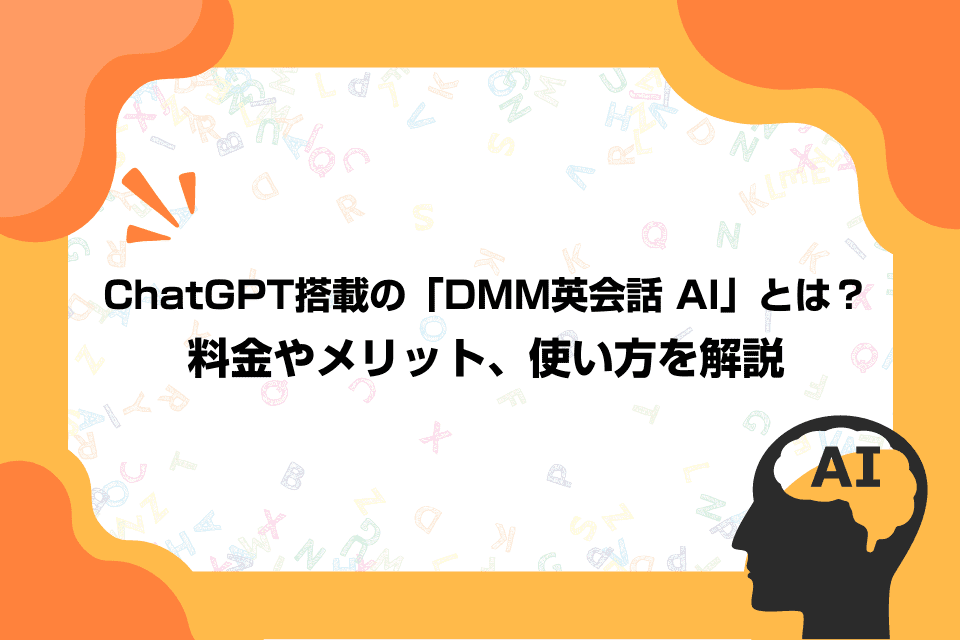
.jpg)
.jpg)
-1.jpg)
.jpg)


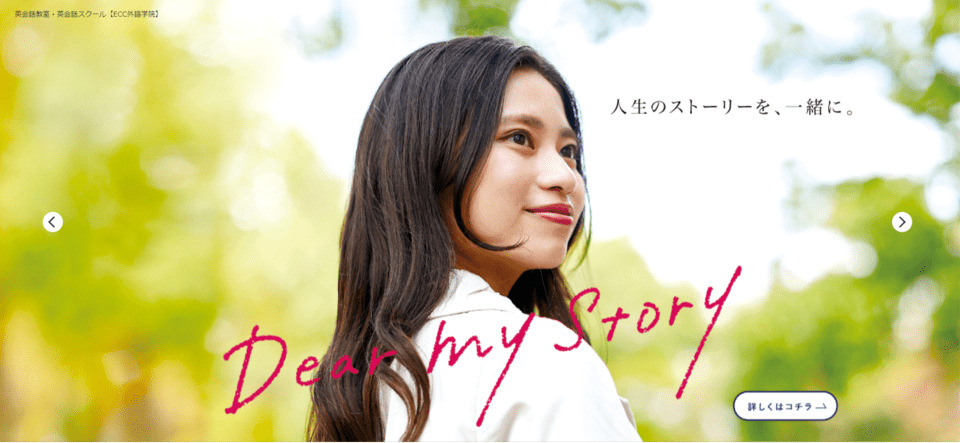


.jpg)

-01.jpg)

-01.jpg)
-toeic.png)




-01.jpg)
あなたの英語学習を一緒に応援してくれる仲間たち
明治大学サービス創新研究所客員研究員/ライター
2019年からオンライン英会話を始め、現在4年目。世界各国の人とオンライン英会話を通じて知り合った人たちと友達になり、現在は各国に友達ができるまでに。オンライン英会話、英語コーチング、TOEICスクールなど、複数を受講経験あり。目標は、海外の教育者と意見交換したり、映画プロデューサーにインタビューすること。
高校時代に英語を猛勉強し、校内偏差値が40→80にUP。大学では英語教育を専攻し、4年次にオーストラリアのパースへ留学。「話す」「聞く」にフォーカスを置いて、現地の人々や世界各国の留学生と交流を深めた。その結果、ケンブリッジ英検B2、TOEIC400→835を取得。現在は、海外へ行きたいけど英語に不安がある人たちのサポートや後押しをしている。
元こども英会話教室の主任講師。4年間イギリス人講師とペアでティーチングしつつ、日々の会話の中から日英の文化の違いにも興味を持つ。海外在住歴や留学経験などはなく、地道に英語学習した後に講師へ。教室型英会話とオンライン英会話の受講経験あり。これらの経験を活かし現在は英語関係の記事を執筆している。
夢はライター活動をしながら旅をすること。各土地で輝いている人を見つけてインタビューし、頑張る人を応援するメディアを作りたい。
米国にて学士留学3年間と英語での仕事を20年経験。
サイエンス・ビジネスおよび日常生活の話題まで幅広いジャンルの英語を得意としています。
TOEIC945と英語経験を生かして、英語が苦手な方をサポートできるようブログ執筆活動を始めました。
WEBライターとしても活躍中。海外現地情報をリサーチしたライティングを得意としています。
英語の楽しさと奥深さを読者の皆様にお届けできますように。
10歳の時に通い始めた英会話教室の影響で英語に興味を持ち、以来20年以上にわたりずっと英語の勉強を続けている。
高校生の時に英語スピーチコンテストで優勝経験あり。語学の有名な某四年制大学の外国語学部英語学科を卒業。留学経験はないながらも、TOEIC L&Rテストでは独学で925点を取得。現在は都内外資系企業にて、日々英語を使いながら仕事をしている。
また、会社員の傍らWebライターとして、英語学習コンテンツの制作にも携わっている。
株式会社EduMe 代表
アメリカ大学院にて英語教授法(TESL: Teaching English as Second Language) の修士を取得。
その後、高校生や大学生に英語を教えて20年。TOEFL指導や海外大学留学支援なども手がける。
現在は、子供向け英語プログラミング塾「ワンダーコード」を運営。
中高英語教員免許 / 英検1級 / TOEIC980点
20歳に受けたTOEICは480点→45歳、二度目の挑戦では915点。
夫はイギリス人で家族で日本在住7年目。双方ともに西ヨーロッパに親戚が多く移住しており、西ヨーロッパのの知識が豊富。
字幕翻訳に関わる前は日本語講師として日本語を英語を使って教えていた。
現在、本業の傍らで小規模の英会話教室運営中。J-SHINE、TESOL取得。イギリス老舗のジョリーフォニックスの講習会を修了。
将来の夢は、60歳までにイギリスの大学に留学すること。
中学のころから英語好きが始まる。高校のころは、英語の教科書を丸暗記するほど音読に没頭。英語だけでは飽き足らず、大学ではフランス語を専攻し、言語学や音声学も学ぶ。ただ、英語好きはずっと変わらず、その後も勉強を続け、社会人になってから英検1級を取得。
自分の学んだ英語学や言語学を単なる知識で終わらせず、他の人が活用できるように、実用的な形で提供したいと考えている。
最近ではKindle本執筆にも挑戦し、『単語と単語の意外な関係』などの本を書いた。
私立中高英語教師歴10年。長期留学経験なしで、オンライン英会話などを活用して英語学習を継続。
TOEICは920点を取得。普段は中学生や高校生に英語を指導。
英語の苦手克服から、難関大学受験対策まで幅広く対応。
オンライン英会話5年目。さらに英語力向上を目指して日々学んでいます。
慶應法学部卒→JTCで海外事業に携わるも英語力が足りずに挫折→転職→妊娠・出産で退職→35歳で一念発起して英語を学び直し。留学・海外経験なしから独学でTOEIC900点を獲得→翻訳者。
ELSA speakには絶賛ハマり中。英検1級と通訳案内士取得を目指している。
元高校英語教師 / ライター・翻訳者
高校社会科教師の傍ら英語を学び、英語教員免許を取得。その後大手英会話スクールに通いTOEICで930点を取得。長野オリンピックでVIP接遇の通訳ボランティアを経験し、高校英語教師に転身。55歳にして英語検定1級を取得する。苦労して英語を学んだため、英語学習の大変さを誰よりも知っている。現在は、オンラインでスペイン語を学び、スペイン語の通訳を目指している。
1年の留学経験あり。帰国後は英語力向上のため、オンライン英会話で会話を学んだり発音矯正のスクールに通う。
その後、独学でTOEIC885点取得。英語力を活かし、前職は子ども向けのオンライン英会話講師として活躍。
現在は2児のワーママとして親子でお家英語に取り組み中です。
北海道:札幌 / 函館 / 旭川
青森県:青森
岩手県:岩手
宮城県:仙台
秋田県:秋田
山形県:山形
福島県:福島 / 会津若松 / 郡山 / いわき
茨城県:水戸 / 日立 / つくば
栃木県:宇都宮 / 小山
群馬県:群馬 / 前橋 / 高崎
埼玉県:大宮 / 浦和 / 川越 / 熊谷 / 所沢 / 上尾 / 草加 / 入間 / 志木 / 春日部
千葉県:千葉 / 幕張 / 本八幡 / 船橋 / 松戸 / 津田沼 / 柏 / 浦安
東京都:飯田橋 / 神田 / 東京 / 有楽町 / 銀座 / 日本橋 / 六本木 / 六本木一丁目 / 溜池山王 / 赤坂 / 田町 / 新橋 / 新宿 / 高田馬場 / 四谷 / 茗荷谷 / 御茶ノ水 / 秋葉原 / 上野 / 錦糸町 / 豊洲 / 門前仲町 / 品川 / 大崎 / 大井町 / 五反田 / 目黒 / 自由が丘 / 中目黒 / 蒲田 / 千歳烏山 / 下北沢 / 三軒茶屋 / 渋谷 / 恵比寿 / 中野 / 池袋 / 赤羽 / 日暮里 / 練馬 / 北千住 / 西新井 / 金町 / 葛西・西葛西 / 八王子 / 立川 / 吉祥寺 / 調布 / 町田 / 国分寺 / 多摩センター / 田無 / ひばりが丘
神奈川県:横浜 / 金沢文庫・金沢八景 / 新横浜 / 日吉 / 戸塚 / 青葉台 / 川崎 / 溝の口 / 新百合ヶ丘 / 相模大野 / 本厚木 / 鎌倉 / 藤沢 / 小田原
新潟県:新潟
富山県:富山
石川県:金沢 / 小松
福井県:福井
山梨県:山梨 / 甲府
長野県:長野 / 松本
岐阜県:岐阜 / 大垣 / 多治見 / 各務原
静岡県:静岡 / 浜松 / 沼津 / 富士 / 藤枝
愛知県:名古屋 / 岡崎 / 一宮 / 半田 / 豊田 / 安城 / 犬山 / 小牧 / 大府 / 岩倉
三重県:津 / 四日市 / 桑名 / 鈴鹿 / 松阪
滋賀県:滋賀
京都府:京都 / 北大路 / 山科
大阪府:大阪 / 天王寺 / 京橋 / 梅田 / 難波 / 豊中 / 千里中央 / 吹田 / 高槻 / 枚方 / 茨木
兵庫県:神戸 / 三宮 / 西神中央 / 姫路 / 西宮 / 芦屋
奈良県:奈良 / 生駒
和歌山県:和歌山
鳥取県:鳥取 / 米子
島根県:松江 / 出雲
岡山県:岡山 / 倉敷
広島県:広島 / 呉 / 福山
山口県:山口 / 下関 / 宇部
徳島県:徳島
香川県:高松
愛媛県:松山
高知県:高知
福岡県:福岡 / 博多 / 北九州 / 久留米
佐賀県:佐賀
長崎県:長崎市 / 佐世保
熊本県:熊本
大分県:大分
宮崎県:宮崎
鹿児島県:鹿児島
沖縄県:沖縄
埼玉県 / さいたま市 / さいたま市西区 / さいたま市北区 / 土呂駅 / さいたま市大宮区 / 鉄道博物館駅 / 見沼区 / さいたま市中央区 / 与野本町駅 / 桜区 / さいたま市浦和区 / 与野駅 / 北浦和駅 / 浦和駅 / さいたま市南区 / 武蔵浦和駅 / 南浦和駅 / さいたま市緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 本川越駅 / 霞ヶ関駅 / 熊谷市 / 籠原駅 / 川口市 / 東川口駅 / 鳩ヶ谷駅 / 行田市 / 秩父市 / 所沢市 / 狭山ヶ丘 / 小手指町 / 飯能市 / 加須市 / 本庄市 / 児玉駅 / 東松山市 / 春日部市 / 一ノ割駅 / 狭山市 / 新狭山駅 / 羽生市 / 鴻巣市 / 深谷市 / 上尾市 / 草加市 / 谷塚駅 / 越谷市 / 南越谷駅 / 北越谷駅 / せんげん台駅 / 蕨市 / 蕨駅 / 戸田市 / 戸田公園駅 / 入間市 / 武蔵藤沢駅 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 桶川市 / 久喜市 / 八潮市 / みずほ台駅 / 鶴瀬駅 / 三郷市 / 蓮田市 / 坂戸市 / 鶴ヶ島市 / 吉川市 / ふじみ野市 / 白岡市 / 伊奈町 / 小川町 / 上里町 / 寄居町 / 杉戸町
千葉県 / 千葉市 / 千葉市中央区 / 千葉中央駅 / 西千葉駅 / 蘇我駅 / 千葉市花見川区 / 幕張本郷駅 / 幕張駅 / 新検見川駅 / 稲毛区 / 千葉市若葉区 / 千城台駅 / 千葉市緑区 / 鎌取駅 / あすみが丘 / おゆみ野駅 / 土気駅 / 千葉市美浜区 / 海浜幕張駅 / 稲毛海岸駅 / 市川市 / 市川大野駅 / 行徳駅 / 南行徳駅 / 本八幡駅 / 船橋市 / 西船橋駅 / 南船橋駅 / 船橋日大前駅 / 船橋法典駅 / 北習志野駅 / 馬込沢駅 / 薬園台駅 / 前原駅 / 滝不動駅 / 夏見台 / 木更津市 / 松戸市 / 松戸駅 / 新松戸駅 / 新八柱駅 / 馬橋駅 / 五香 / みのり台駅 / 野田市 / 川間駅 / 茂原市 / 成田市 / 佐倉市 / 京成臼井駅 / ユーカリが丘 / 東金市 / 旭市 / 習志野市 / 津田沼 / 津田沼駅 / 京成津田沼駅 / 谷津駅 / 柏市 / 柏の葉キャンパス駅 / 柏駅 / 豊四季駅 / 市原市 / 五井駅 / ちはら台駅 / 流山市 / 南流山駅 / 流山おおたかの森駅 / 八千代市 / 八千代中央駅 / 八千代緑が丘駅 / 八千代台駅 / 勝田台 / 我孫子市 / 天王台駅 / 鎌ケ谷市 / 新鎌ケ谷 / 君津市 / 浦安市 / 新浦安駅 / 四街道市 / 袖ケ浦市 / 印西市 / 千葉ニュータウン中央駅 / 白井市 / 富里市 / 匝瑳市 / 香取市 / 佐原駅 / 山武市
23区
千代田区 / 御茶ノ水 / 神田 / 飯田橋駅 / 中央区 / 銀座 / 月島 / 勝どき / 小伝馬町駅 / 人形町駅 / 築地駅 / 日本橋駅 / 港区 / 高輪 / 芝浦 / 青山 / 赤坂 / 外苑前駅 / 赤坂見附駅 / 田町駅 / 白金台駅 / 白金高輪駅 / 麻布十番駅 / 六本木駅 / 新宿区 / 四谷 / 四ツ谷駅 / 曙橋駅 / 神楽坂駅 / 早稲田駅 / 高田馬場駅 / 落合駅 / 落合南長崎駅 / 文京区 / 護国寺駅 / 千駄木駅 / 本郷三丁目駅 / 本駒込駅 / 茗荷谷駅 / 台東区 / 秋葉原 / 浅草 / 谷中 / 御徒町駅 / 三ノ輪駅 / 上野駅 / 蔵前駅 / 入谷駅 / 墨田区 / 向島 / 押上駅 / 錦糸町駅 / 両国駅 / 江東区 / 北砂 / 亀戸駅 / 清澄白河駅 / 東陽町駅 / 豊洲駅 / 木場駅 / 門前仲町駅 / 有明駅 / 品川区 / 戸越銀座駅 / 新馬場駅 / 大井町駅 / 品川シーサイド駅 / 不動前駅 / 武蔵小山駅 / 目黒区 / 下目黒 / 自由が丘 / 目黒区緑が丘 / 目黒本町 / 学芸大学駅 / 洗足駅 / 中目黒駅 / 都立大学駅 / 祐天寺駅 / 大田区 / 鵜の木駅 / 下丸子駅 / 蒲田駅 / 久が原駅 / 雑色駅 / 西馬込駅 / 石川台駅 / 雪が谷大塚駅 / 大森駅 / 池上駅 / 田園調布駅 / 馬込駅 / 梅屋敷駅 / 糀谷駅 / 世田谷区 / 三軒茶屋 / 駒沢 / 桜新町 / 池尻大橋駅 / 二子玉川駅 / 等々力駅 / 上野毛駅 / 用賀駅 / 奥沢駅 / 下北沢駅 / 梅ヶ丘駅 / 豪徳寺 / 上町駅 / 経堂駅 / 千歳船橋駅 / 祖師ヶ谷大蔵駅 / 成城学園前駅 / 明大前駅 / 下高井戸駅 / 上北沢駅 / 芦花公園駅 / 千歳烏山駅 / 砧 / 渋谷区 / 広尾 / 笹塚 / 初台 / 恵比寿駅 / 代々木駅 / 代々木公園駅 / 代々木上原駅 / 代々木八幡駅 / 代官山駅 / 幡ヶ谷駅 / 中野区 / 鷺宮 / 中野坂上駅 / 東中野駅 / 野方駅 / 杉並区 / 阿佐ヶ谷 / 久我山 / 上井草 / 井荻駅 / 永福町駅 / 荻窪駅 / 下井草駅 / 高井戸駅 / 高円寺駅 / 西永福駅 / 西荻窪駅 / 東高円寺駅 / 浜田山駅 / 方南町駅 / 豊島区 / 巣鴨 / 駒込駅 / 池袋駅 / 椎名町駅 / 目白駅 / 東京都北区 / 王子 / 赤羽 / 滝野川 / 十条駅 / 田端駅 / 浮間舟渡駅 / 荒川区 / 西日暮里駅 / 町屋駅 / 南千住駅 / 板橋区 / 上板橋 / ときわ台駅 / 下赤塚駅 / 成増駅 / 東武練馬駅 / 板橋本町駅 / 練馬区 / 桜台 / 上石神井 / 光が丘駅 / 江古田駅 / 小竹向原駅 / 石神井公園駅 / 大泉学園駅 / 地下鉄赤塚駅 / 氷川台駅 / 富士見台駅 / 武蔵関駅 / 平和台駅 / 練馬高野台駅 / 練馬春日町駅 / 足立区 / 綾瀬 / 五反野駅 / 舎人駅 / 西新井駅 / 竹ノ塚駅 / 北千住駅 / 六町駅 / 葛飾区 / 金町 / お花茶屋駅 / 亀有駅 / 京成立石駅 / 新小岩駅 / 江戸川区 / 一之江 / 小岩 / 西葛西 / 葛西駅 / 京成小岩駅 / 篠崎駅 / 瑞江駅 / 船堀駅 / 平井駅
23区外
八王子市 / めじろ台駅 / 京王堀之内駅 / 南大沢駅 / 八王子みなみ野駅 / 立川市 / 武蔵野市 / 吉祥寺 / 武蔵境駅 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 分倍河原駅 / 多磨駅 / 昭島市 / 拝島駅 / 調布市 / 深大寺 / つつじヶ丘駅 / 国領駅 / 仙川駅 / 町田市 / つくし野駅 / 玉川学園前駅 / 成瀬駅 / 多摩境駅 / 鶴川駅 / 南町田グランベリーパーク駅 / 小金井市 / 東小金井駅 / 武蔵小金井駅 / 小平市 / 花小金井 / 一橋学園駅 / 日野市 / 久米川町 / 八坂駅 / 国分寺市 / 国立市 / 矢川駅 / 牛浜駅 / 狛江市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 京王多摩センター駅 / 聖蹟桜ヶ丘駅 / 稲城市 / 羽村市 / あきる野市 / 秋川駅 / ひばりヶ丘 / 田無駅 / 保谷駅 / 瑞穂町
神奈川県 / 横浜市 / 横浜市鶴見区 / 横浜市神奈川区 / 東神奈川駅 / 片倉町駅 / 横浜市西区 / みなとみらい駅 / 戸部駅 / 横浜市中区 / 元町 / 横浜市南区 / 井土ヶ谷駅 / 弘明寺駅 / 横浜市保土ケ谷区 / 天王町駅 / 和田町駅 / 横浜市磯子区 / 根岸駅 / 杉田駅 / 洋光台駅 / 横浜市金沢区 / 金沢八景駅 / 金沢文庫駅 / 能見台駅 / 横浜市港北区 / 新横浜駅 / 菊名駅 / 日吉駅 / 日吉本町駅 / 綱島駅 / 大倉山 / 戸塚区 / 東戸塚駅 / 横浜市港南区 / 上大岡駅 / 横浜市旭区 / 二俣川駅 / 希望ヶ丘駅 / 鶴ヶ峰駅 / 横浜市緑区 / 長津田駅 / 中山駅 / 鴨居 / 横浜市瀬谷区 / 三ツ境駅 / 栄区 / 本郷台駅 / 横浜市泉区 / 横浜市青葉区 / あざみ野 / 市ケ尾町 / 青葉台 / たまプラーザ駅 / 江田駅 / 市が尾駅 / 藤が丘駅 / 横浜市都筑区 / センター南駅 / センター北駅 / 仲町台駅 / 川崎市 / 川崎市川崎区 / 川崎駅 / 川崎市幸区 / 鹿島田 / 川崎市中原区 / 元住吉駅 / 新丸子駅 / 武蔵小杉駅 / 武蔵新城駅 / 武蔵中原駅 / 川崎市高津区 / 溝の口駅 / 梶が谷駅 / 川崎市多摩区 / 登戸駅 / 向ヶ丘遊園駅 / 生田駅 / 中野島駅 / 稲田堤駅 / 川崎市宮前区 / 宮崎台駅 / 宮前平駅 / 川崎市麻生区 / 新百合ヶ丘駅 / 百合ヶ丘駅 / 柿生駅 / 黒川駅 / 相模原市 / 相模原市緑区 / 橋本駅 / 相模原市中央区 / 淵野辺駅 / 相模原市南区 / 相模大野駅 / 小田急相模原駅 / 東林間駅 / 古淵駅 / 横須賀市 / 久里浜 / 衣笠駅 / 平塚市 / 鎌倉市 / 腰越駅 / 藤沢市 / 本鵠沼駅 / 鵠沼海岸駅 / 鵠沼駅 / 辻堂駅 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 秦野市 / 厚木市 / 本厚木駅 / 大和市 / 中央林間駅 / 南林間駅 / つきみ野駅 / 伊勢原市 / 海老名市 / さがみ野駅 / 座間市 / 相武台前駅 / 綾瀬市 / 葉山町 / 寒川町 / 開成町 / 湯河原町
愛知県 / 名古屋市 / 名古屋市千種区 / 覚王山駅 / 星ヶ丘駅 / 池下駅 / 本山駅 / 名古屋市東区 / 名古屋市北区 / 名古屋市西区 / 名古屋市中村区 / 名古屋駅 / 名古屋市中区 / 栄 / 名古屋市金山 / 久屋大通駅 / 名古屋市昭和区 / いりなか駅 / 御器所駅 / 川名駅 / 八事駅 / 名古屋市瑞穂区 / 桜山駅 / 熱田区 / 中川区 / 名古屋市港区 / 名古屋市南区 / 守山区 / 名古屋市緑区 / 徳重駅 / 名古屋市名東区 / 一社駅 / 天白区 / 豊橋市 / 岡崎市 / 一宮市 / 瀬戸市 / 半田市 / 春日井市 / 豊川市 / 津島市 / 碧南市 / 刈谷市 / 東刈谷駅 / 豊田市 / 安城市 / 三河安城駅 / 西尾市 / 蒲郡市 / 常滑市 / 小牧市 / 稲沢市 / 東海市 / 知多市 / 尾張旭市 / 岩倉市 / 日進市 / 赤池町 / 田原市 / 愛西市 / 清須市 / 北名古屋市 / みよし市 / あま市 / 長久手市 / 東郷町 / 扶桑町 / 蟹江町 / 武豊町
大阪府 / 大阪市 / 都島区 / 大阪市福島区 / 海老江 / 此花区 / 大阪市西区 / 阿波座駅 / 大阪市港区 / 弁天町駅 / 大正区 / 大阪市天王寺区 / 大阪上本町駅 / 浪速区 / 西淀川区 / 大阪市東淀川区 / 淡路駅 / 大阪市東成区 / 今里駅 / 生野区 / 大阪市旭区 / 城東区 / 大阪市阿倍野区 / 西田辺駅 / 大阪市住吉区 / 東住吉区 / 西成区 / 大阪市淀川区 / 三国駅 / 東三国駅 / 大阪市鶴見区 / 放出駅 / 住之江区 / 大阪市平野区 / 喜連瓜破駅 / 大阪市北区 / 梅田 / 中崎町駅 / 南森町駅 / 大阪市中央区 / なんば駅 / 森ノ宮駅 / 谷町四丁目駅 / 天満橋駅 / 堺市 / 堺区 / 堺市中区 / 深井駅 / 堺市東区 / 北野田駅 / 堺市西区 / 鳳駅 / 堺市南区 / 泉ヶ丘駅 / 堺市北区 / なかもず駅 / 美原区 / 岸和田市 / 豊中市 / 千里中央駅 / 蛍池駅 / 少路駅 / 曽根駅 / 緑地公園駅 / 池田市 / 吹田市 / 岸辺駅 / 江坂駅 / 千里山駅 / 桃山台駅 / 泉大津市 / 高槻市 / 貝塚市 / 守口市 / 大日駅 / 枚方市 / 茨木市 / 南茨木駅 / 彩都西駅 / 八尾市 / 近鉄八尾駅 / 泉佐野市 / 富田林市 / 寝屋川市 / 河内長野市 / 松原市 / 大東市 / 住道駅 / 和泉市 / 和泉中央駅 / 箕面市 / 柏原市 / 羽曳野市 / 門真市 / 摂津市 / 千里丘駅 / 東大阪市 / 鴻池新田駅 / 若江岩田駅 / 徳庵駅 / 八戸ノ里駅 / 四條畷市 / 交野市 / 金剛駅 / 阪南市 / 熊取町
神戸市 / 神戸市東灘区 / 六甲アイランド / 御影駅 / 神戸市灘区 / 六甲駅 / 兵庫区 / 長田区 / 神戸市須磨区 / 板宿駅 / 神戸市垂水区 / 舞子駅 / 神戸市北区 / 鈴蘭台駅 / 神戸市中央区 / 三宮 / 神戸市西区 / 西神中央駅 / 学園都市駅 / 伊川谷駅 / 姫路市 / 山陽網干駅 / 尼崎市 / 園田駅 / 塚口駅 / 武庫之荘駅 / 立花駅 / 明石市 / 魚住町 / 西新町駅 / 大久保駅 / 西宮市 / 甲子園駅 / 苦楽園口駅 / 洲本市 / 芦屋市 / 伊丹市 / 加古川市 / 東加古川駅 / 赤穂市 / 西脇市 / 宝塚市 / 三木市 / 高砂市 / 川西市 / 小野市 / 三田市 / 丹波市 / たつの市 / 猪名川町 / 土山駅
福岡県 / 北九州市 / 門司区 / 若松区 / 戸畑区 / 小倉北区 / 北九州市小倉南区 / 下曽根駅 / 八幡東区 / 八幡西区 / 福岡市 / 福岡市東区 / 香椎駅 / 箱崎宮前駅 / 和白駅 / 博多区 / 福岡市中央区 / 福岡市天神 / 西鉄平尾駅 / 六本松駅 / 福岡市南区 / 井尻駅 / 福岡市西区 / 姪浜駅 / 福岡市城南区 / 七隈 / 福岡市早良区 / 西新駅 / 久留米市 / 飯塚市 / 田川市 / 柳川市 / 八女市 / 筑後市 / 行橋市 / 中間市 / 小郡市 / 筑紫野市 / 春日市 / 大野城市 / 宗像市 / 太宰府市 / 古賀市 / うきは市 / 朝倉市甘木 / 糸島市 / 糟屋郡 / 篠栗町 / 志免町 / 新宮町 / 粕屋町 / 苅田町